【忘れず申請を!】歯科矯正も医療費控除対象に!控除される条件と申請方法・計算方法
【監修医:矯正歯科学会 認定医&指導医 増岡 尚哉】
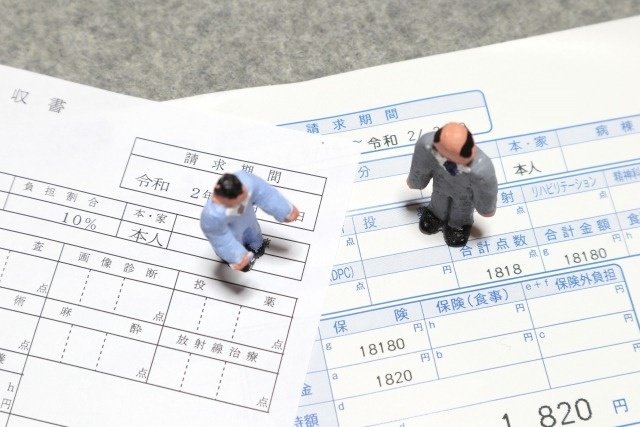
歯科矯正では、一般的に40万円~80万円程度かかるとされています。決して安くはない治療費を軽減する上で、医療費控除があります。
医療費控除とはどのような仕組みか、そして医療費控除が適用される条件、さらには申請方法や計算方法をご紹介します。歯科矯正を検討している方はぜひご参考にしてみてください。
【目次】
1、歯科矯正で医療費控除の対象になるのはどんな時?
2、医療費控除制度を利用できる条件
①家族の年間の医療費が原則として10万円以上である
②治療目的が審美目的でない
3、医療費控除の対象となる費用
4、分割払いやデンタルローンを利用した場合も医療費控除対象となる
5、医療費控除で所得税がいくら戻ってくるのか?
①医療費控除額の計算方法
②還付金の計算方法
6、確定申告で医療費控除を申請すれば住民税も減税に
7、医療費控除を申請するまでの流れ
歯科矯正で医療費控除の対象になるのはどんな時?
医療費控除は、1年間に支払った医療費合計が所定の額より多く支払っている場合、確定申告することで、納めた所得税の一部が戻ってくるという制度です。
自営業の人がこの制度を利用すれば確定申告時に納める税金が安くなります。
企業に勤めている人ならば、給料から所得税を天引きされている場合がほとんどなので、そのときは確定申告することで還付金という形でお金が戻ってきます。
医療費控除制度を利用できる条件
医療費控除を受けるためには、以下の条件が必要となります。
①家族の年間の医療費が原則として10万円以上である
保険金などで支払いが補填された金額を除き、年間で10万円以上の治療費がかかった場合にこの制度を利用できます。
ただし、年間の総所得が200万円未満の場合は10万円でなく、所得の5%を引いた金額から利用可能です。例えば、年間所得が190万円であれば190×0.05=9.5万円以上の治療費がかかった場合となります。
この治療費は生計を一にしている家族分の合計で見積もられます。
つまり生活費を共有している家族分のことです。
一緒に住んでいなくても仕送りのやり取りがある場合は生計を一にしていると言え、そこに当てはまる家族全員分の治療費合計が10万円か一定の金額を超えていれば税金が安くなります。
②治療目的が審美目的でない
歯科矯正において医療費控除の対象となるのは、審美目的ではなく医療目的で歯列矯正が必要と認められる場合とされています。
例えば、お子さまで歯や顎の成長を促す必要があるような場合や、成人でかみ合わせなど機能的な問題を改善する場合の治療などです。
もし、すでに当院で歯科矯正をしていて、ご自身のケースが医療費控除の対象になるかご不明な場合は、スタッフまでお気軽にご相談をください。
【子どもの場合(例)】
・不正咬合が顎や歯の成長を阻害している
・発音が不明瞭で改善の必要がある など
【大人の場合】
・重度な出っ歯で食べ物を噛み切れない
・受け口、開咬などで発音が不明瞭 など
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となる医療費に含められるものは以下のものです。
【医療費に含められるもの】
- 診察代、検査代
- 矯正装置料
- 矯正器具の調整料・処置料
- 治療に必要な医薬品の費用
- 通院のための交通費(交通公共機関)※通院困難な方の場合、タクシー代金が認められる場合もあります。
基本的に治療に必要となるものは全て医療費として含めることができます。
逆に含まれないものとして、以下のものが挙げられます。
【医療費に含められないもの】
- 通院の際に使用した自家用車のガソリン代・駐車場代
- 予防や健康増進のために使用した医薬品の費用
- デンタルローンや分割払いでかかった金利
- 診断書
もし治療を受けるのがお子さんならば付き添い人の交通費まで対象になります。ただし、これは公共交通機関を使った場合に限られます。個人の自動車で通った際のガソリン代などは対象外となるので注意してください。
交通費の申請にあたり原則的に領収書が必要でありますが、バスや電車など領収書が出ない場合、診察券などを駆使し、通院した日付やそのためにかかった交通費をメモするようにすればよいでしょう。
また、歯の治療の際に使われるポーセンや金は高価なものにはなりますが、これは問題なく医療費控除の対象範囲内になります。これらの素材は確かに高価なものですが、歯の治療では一般的に使われているものだからです。一般的な歯の治癒額とした際に非常識的な金額でないかという点も判断基準になっています。
また、この他に金額がかかるのは診断書です。こ自費になりますが、必ずしも申請の際に必要な書類ではありません。もし診断書なしでも問題ない場合、診断書の依頼をしないようにしましょう。
分割払いやデンタルローンを利用した場合も医療費控除対象となる
歯科医院の分割払いやデンタルローンを使用した場合も、医療費控除の対象となります。歯科医院の独自の分割払いを利用した場合は、その年に支払った分が医療費控除の対象となります。
デンタルローンを使用した場合は、信販会社が矯正費用を一旦立て替え払いするという形になるので、ローンを契約した年に医療費控除として申告できます。なお、申告時に、歯科医院の領収書がない場合もありますが、その場合はデンタルローンの契約書は信販会社又は領収書を税務署に提出できます。デンタルローンにかかった金利や手数料は医療費控除の対象外となるので、ご注意ください。
医療費控除で所得税がいくら戻ってくるのか?
では、実際に医療費控除でいくらお得になるのか、知りたいところですよね。
医療費控除額に収入別の税率をかけることで、戻り額(還付金)がわかります。
まずは、医療費控除額を求めます。
①医療費控除額の計算方法
医療費控除は、総所得が200万円以上か未満かで計算のやり方が異なります。
ここでいう総所得とは、年間収入から給与所得控除などを引いた所得となります。つまり手取りの金額となります。
医療費控除額の上限は200万円です。医療費控除額が200万円を超えた場合も、200万円分しか適用されません。
また後述しますが、医療費控除額と実際に還付される(戻ってくる)金額は異なりますのでご注意ください。
医療費控除額の計算式は以下の通りです。
(A)年間医療費の合計額
その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費用の合計額
(B)保険金などの補てん金額
民間の生命保険などの入院費給付金や手術給付金、健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金など
(C)※10万円
総所得額が200万円以上なら10万円を差し引きますが、200万円未満であれば、総所得額5%をかけた分を差し引きます。
●総所得が200万円以上…10万円
●総所得が200万円未満…総所得×5%の額
これに合わせて、総所得額が200万円以上のAさん一家と、200万円未満のBさん一家で、医療費控除額を計算してみます。
【Aさん一家の医療費控除額】
例えば、Aさん一家の総所得が夫300万、妻200万で、合計500万円、年間の治療や通院費などの年間医療費が80万円、その医療費を民間の保険金や健康保険などで20万円補填した場合は、以下のような額になります。
(A)80万-(B)20万-(C)10万=50万円
【Bさん一家の医療費控除額】
Bさん一家の総所得が190万円で、医療費が20万円、そのうち健康保険などで5万円を補填した場合、総所得額が200万円未満となるので、医療費より差し引かれる金額は総所得190万×5%=9.5万円となります。
(A)20万-(B)5万-(C)9.5万=5.5万円
②還付金の計算方法
次にどれだけ戻ってくるのか、還付金の計算方法をお教えします。
先ほど算出した医療費控除額に下記の税率を乗算します。
| 所得合計金額(課税所得額) | 税率 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円以上 | 45% |
(2022年12月現在 参照:国税省HP)
この表に合わせて、上記のAさん一家、Bさん一家を例に還付金を計算してみます。
【Aさん一家の還付金】
Aさん一家の総所得額は500万円となりますので、税率は20%となります。
50万円×20%=10万円
Aさん一家は10万円が還付金として戻ってくることになります。
【Bさん一家の還付金】
Bさん一家の総所得は190万円となるので、税率は5%となります。
5.5万円×5%=2,750円
Bさん一家の還付金は、2,750円となります。
確定申告で医療費控除を申請すれば住民税も減税に
確定申告で医療費控除を申請すると、翌年の住民税も自動的に安くなります。
住民税の控除は、所得額に関係なく医療費控除額の10%となります。確定申告で医療費控除を申請した翌年の6月以降、住民税に反映され、その分が安くなります。
上記の例のAさん、Bさん一家の場合で見た場合、以下の金額が既定の住民税から差し引かれます。
【Aさん一家の住民税控除額】 10万円×10%=1万円
【Bさん一家の住民税控除額】 2,750円×10%=275円
なお、住民税には、所得に応じて課せられる「所得割」と住民に一律に課される「均等割」があり、この「所得割」の部分から上記の控除額が差し引かれ、その分を納めることになります。「均等割」への割引はありませんのでご注意ください。
※還付金のシミュレーションはあくまで医療費のみに注目して計算しています。収入、医療費、住宅ローンなどでも控除の有無等でも控除額が変わりますので、あくまで目安としてご参考ください。
医療費控除を申請するまでの流れ
企業に勤めている人は税金が給料から天引きされている場合がほとんどでしょう。そのため年末に行う年末調整で税金から引かれる金額を調整してその分だけお金が手元に戻ってきます。
しかし、医療費控除は年末調整に含まれていないため、自分で確定申告する必要があります。次に給与を受けている人の場合の確定申告の手順を解説します。
1. 内容と金額の確認し、医療費明細書を作成する
医療費控除の確定申告をする際は、まず、受けた治療内容が客観的に見て本当に必要なものだったと判断できるか確認してください。
次に金額の確認です。「医療費のお知らせ」といった通知が健康保険組合から送られてくるので、そこに記されてある年間でかかった金額に注目しましょう。その金額と治療のためにかかった交通費などの諸費用の合計が10万円を、あるいは所得が200万円未満の場合はその5%の金額を超えていたら、支払った所得税の一部が還付されます。
また、治療費は、生活費を共有している家族と合算できるので、その点も見逃さないようにしてください。
これらの明細書を作成します。
明細書は国税庁のHPより、PDF形式又はエクセル形式でダウンロードできます。お好みの形式をダウンロードし、詳細を書き込んでいきます。
請求書が多い場合は、国税庁が用意した医療費集計フォームを使うと便利です。オンライン上で確定申告書類が作成できる国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、この集計フォームが医療費控除の入力画面で読み込まれ、反映されるので、いちいち入力する手間が省けます。
2.確定申告書を記入し、提出する
医療費控除に必要な確定申告書は国税庁のホームページで作成できます。
勤務先で配られる源泉徴収票をもとに、A様式又はB様式の申告書に記入します。医療費控除の欄に、1で計算した控除額を記入します。
確定申告書を作成したら、税務署に直接持参するか、郵送又はオンライン(e-Tax)で提出します。
申告期間は2月16日~3月15日となっています。
3.還付金の振込確認
還付金の振込までには大体1か月半程度かかります。
多くの人にとって確定申告は慣れておらず、最初は戸惑うことが多いでしょう。当院では医療費控除の申請無料サポートがあるので、ぜひ利用してみてくださいね。
